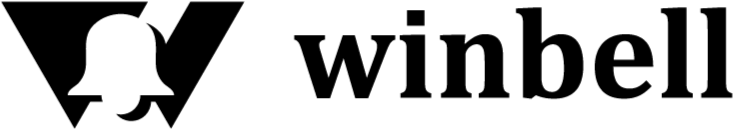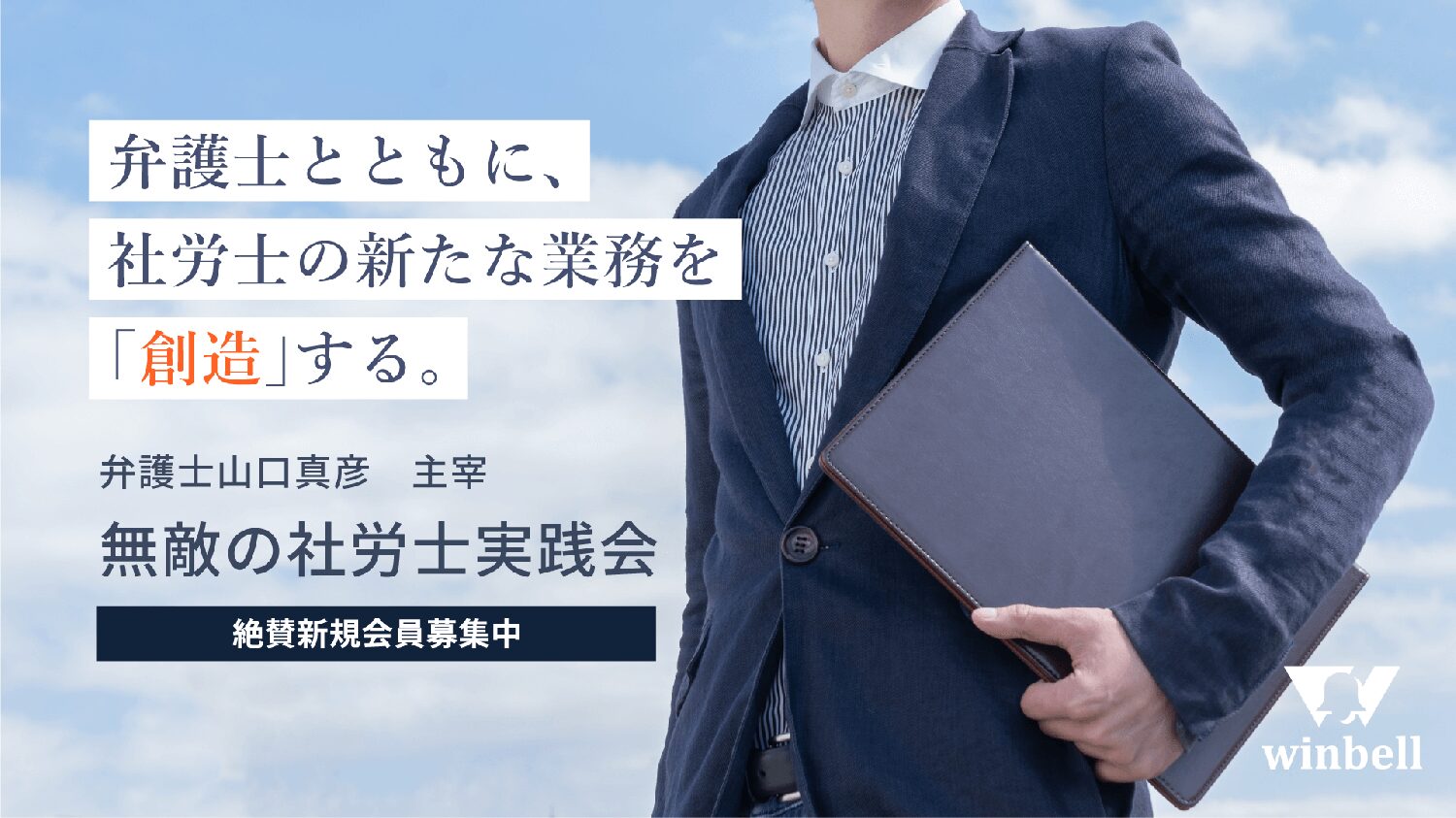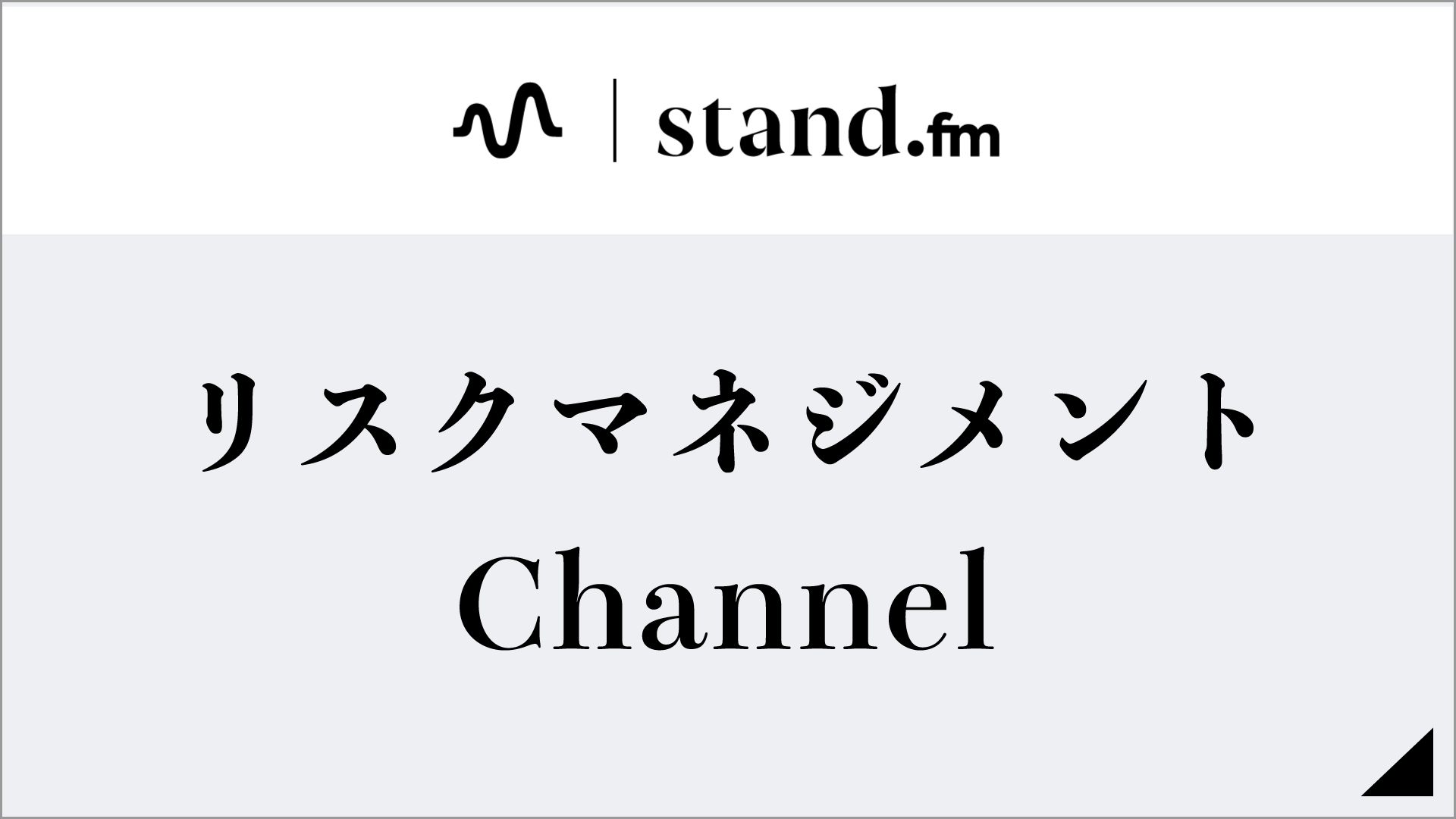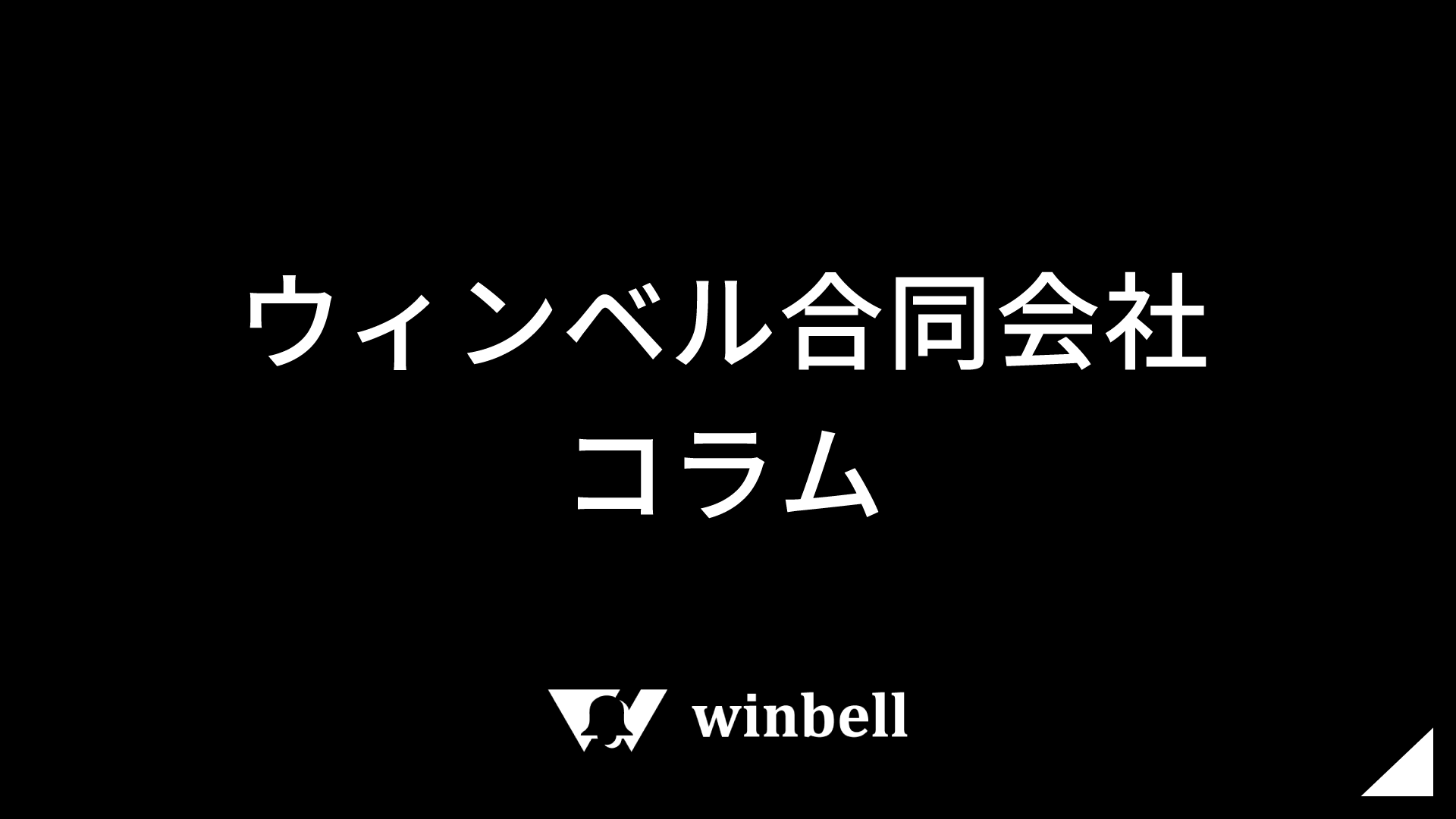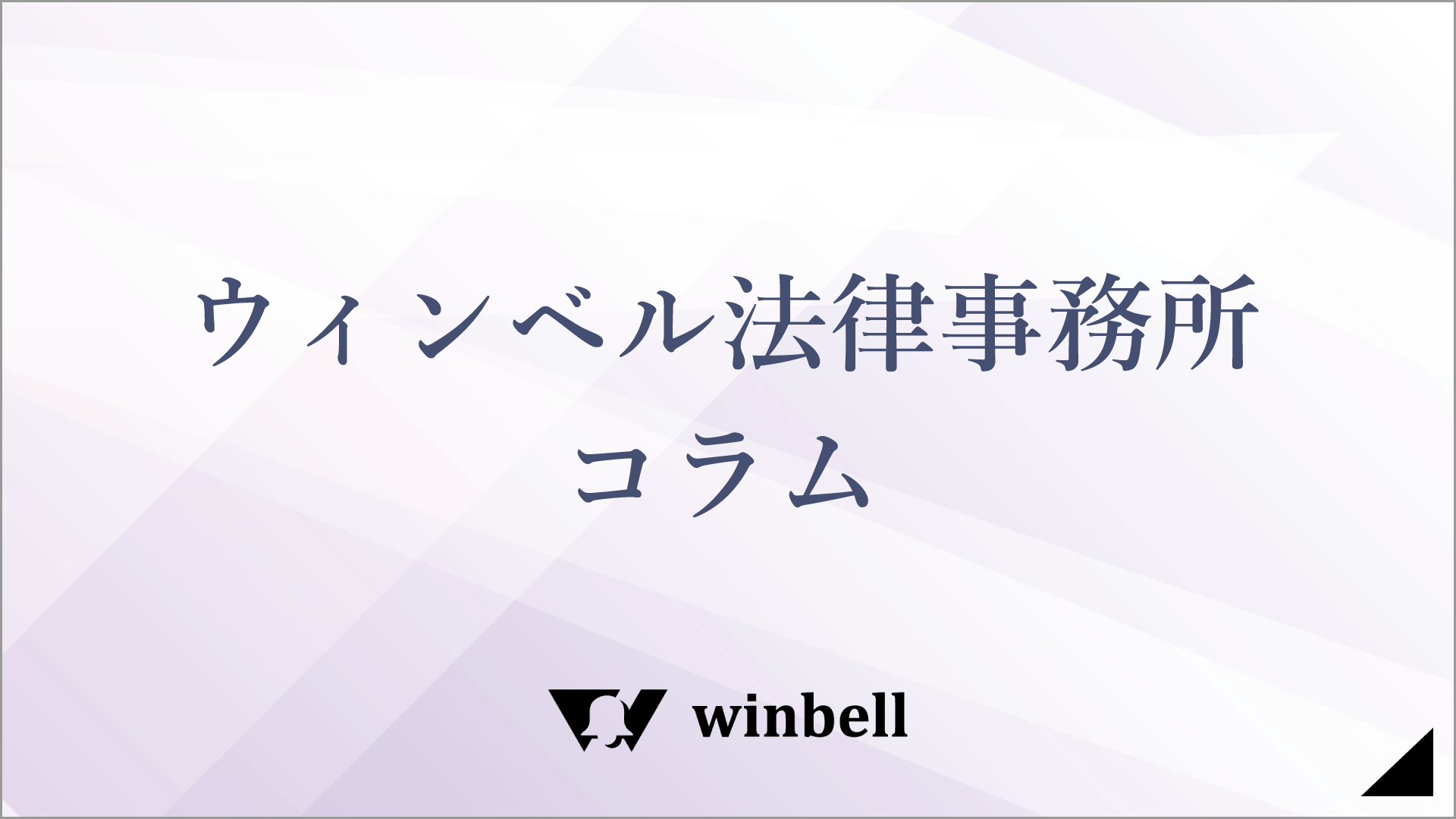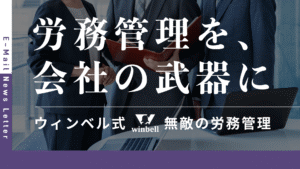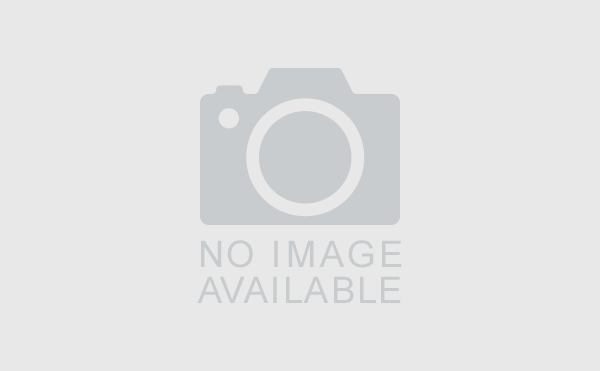休職制度の注意点|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.57

休職制度の注意点

ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日は、質問をいただきましたので、その質問に答えたいと思います。
質問はこちらです。
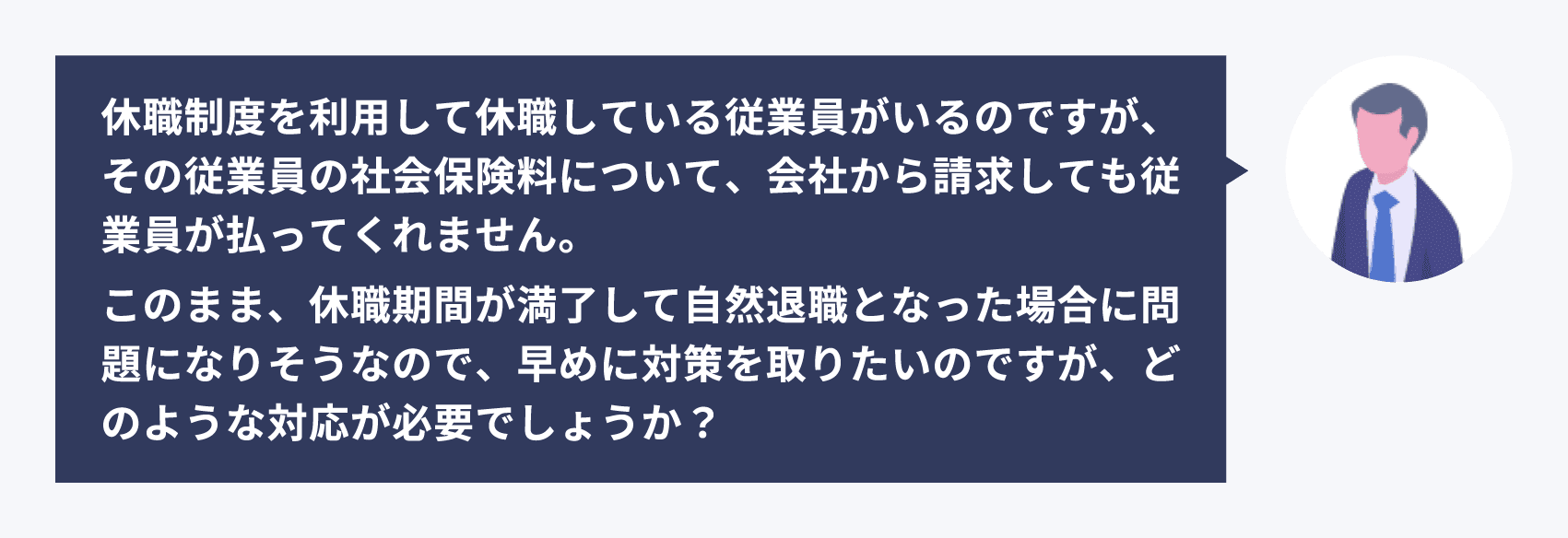
休職制度を利用する場合、従業員の体調などに目が行きがちになって、意外と社会保険料等の従業員負担分をどうするのかは見落としがちな部分ですよね。
しかも、そのまま従業員が退職した場合、回収が困難になることが多々あります。
休職期間が長期にわたれば、その額もそれなりの金額になりますので、しっかり対策を取っておくことをオススメします。
では、具体的にどのような対策を講じればよいのかということですが、やはり一番は「事前の対策」です。
会社が従業員へ休職命令を出す際に、休職期間や休職期間満了時の取り扱いなどを説明すると思うのですが、その際に休職期間中の社会保険料等はその都度会社から請求するという取り決めをしておき、傷病手当金等から支払うように書面で伝えましょう(目安となる金額を口頭で伝えておくと、従業員も安心すると思います。)。
休職命令書の雛形をご用意しましたので、参考にされてください。
ダウンロードはこちら基本的にこのような事前の対策で、概ね問題は解決します。
ただ、これでは上記の質問に回答できていませんので、次は「事後の対策」をお伝えいたします。
具体的な方法としては、相殺が効果的な方法になるかと思います。
たとえば、従業員がそのまま退職した場合は、退職金との相殺という方法が考えられます。
ただし、相殺する場合は、必ず従業員と合意をするようにしてください。
場合によっては、どうせ辞めるんだから相殺には応じませんと言われる可能性もあります。
その場合に備えて、賃金控除に関する労使協定を締結しておけば、問題なく相殺できます(ただし、相殺可能な範囲は、退職金の額の4分の1までになります。)。
その他にも、従業員が復職した場合は、毎月の給与からの相殺も考えられます。
退職金の場合と同様、従業員の合意を取るか労使協定を締結しておくかになります。
ただし、未払の社会保険料等が高額になっている場合は、一気に相殺してしまうと従業員の生活に支障が出る可能性もありますので、数か月に分けて無理のない範囲で相殺するのがよいでしょう。
以上、いかがでしょうか?
休職制度で意外と見落としがちな点になりますので、参考にしていただければと思います。
そして、よい質問をありがとうございました。
皆様もご質問があれば、本メルマガの末尾に質問箱を用意しておりますので、遠慮なくご質問ください!
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱